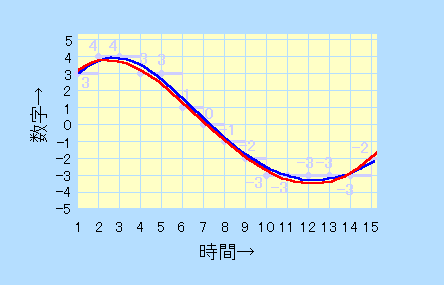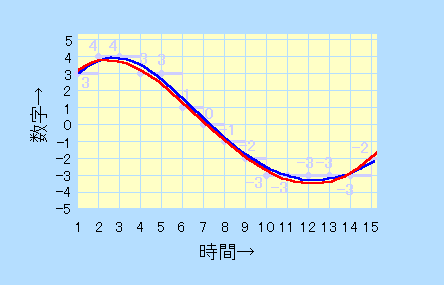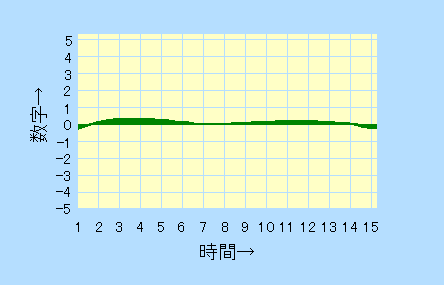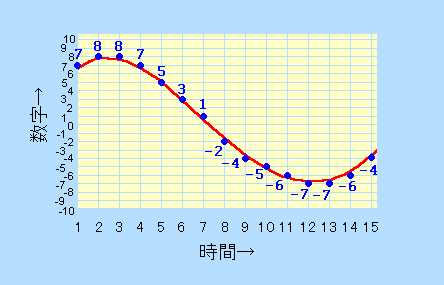目次へ 前のページへ
9.量子化誤差と細かいメッシュ
さあ、結果が出ましたので、さっきの赤い波形、つまり元の波形と比べてみましょう。
どうでしょう。大体元に戻っていますね。
でも少しずれています。時間4のあたりや12のあたりが少し高いですね。なんでズレたんでしょう。
この原因は、最初にステップにに乗せるときにやった四捨五入です。赤い線を青い点になおすときに、量子化のステップが荒いため、誤差が出たわけです。
ちょっと誤差だけ見てみましょうか。つまり赤い波形と青い波形の差だけグラフにしてみます。
どうですか。このように縦方向のステップの荒さから、四捨五入により発生する誤差を量子化誤差といいます。量子化誤差が大きいと音が悪くなりますから、ステップは十分細かい必要があります。
量子化誤差は四捨五入が原因ですから、元のステップ幅の半分を超える事はありません。つまりステップ幅に対してプラスマイナス0.5が最大誤差です。
ですから、ステップの幅を半分にすれば、誤差も半分になります。
ではちょっと、ステップを倍にしてみましょうか。
どうですか。さっきは波形からずいぶん離れたように見えた「青い点」が、赤い波形にくっついてきましたね。量子化誤差が減っているわけです。
そういうわけで、ステップ数は多ければ多いほど(ステップ幅が細かければ細かいほど)よいわけですが、CDでは65536段階のステップを使っています。
勿論ステップ幅を小さくするとデータの桁数が増えますから、記録が大変になります。だいいち変換することも大変なんですね。ですから、このステップ数は無限に増やせるものではないんです。
CDの65536段階というのは、CDの規格を作ったとき、当時の半導体技術でやっと実現できるという非常に難しいものだったんですよ。
(補足)
後で触れますが、この65536というステップは、デジタル用語で「16ビット」という性能を表しています。実はCDの規格を作ったとき、オランダのフィリップス社が提案していたのは「14ビット」でした。これは16384段階しかありません。しかし、これでは音質的に不十分であるというソニーの判断で16ビットを提案し、そのようになったという歴史があります。
(制作/著作 かないまる 2000年7月15日)
(字句修正 2000年8月20日)
(14ビットの値が192384となっていたのを修正 040911)