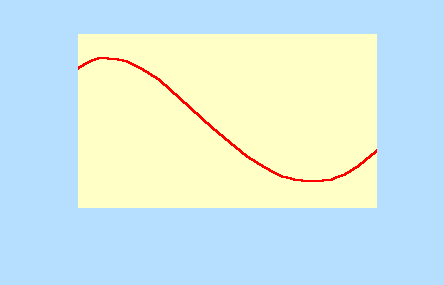
7.
動きのある波形のA/D変換
では、この「数字」の作り方を見て行きましょう。
体温は一回測定すれば終わりで、次は二時間後か、ひょっとすると一カ月後かもしれませんね。しかし、音楽のような場合は、時々刻々と変化して行く様子を伝えなければなりません。
つまりアナログの「波形」をデジタルになおす手順を見て行くわけです。
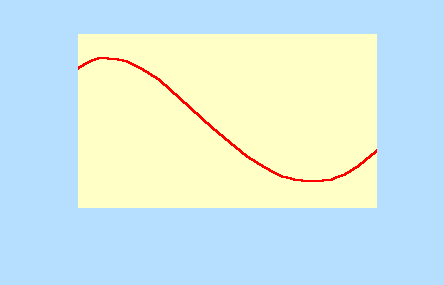
まずこれが元の波形だとします。つまり音楽波形のほんの一部というわけです。
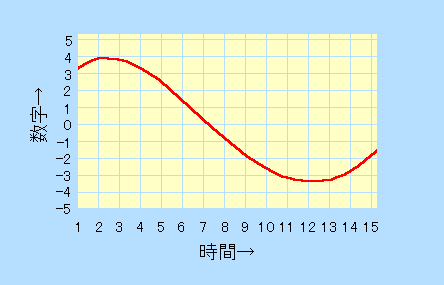
この波形を、一定の間隔の縦線で切ります。横軸は時間です。つまり一定の繰り返し周期でやってくる時間ごとに、この縦線のところで電圧を数字になおす事にします。
ここで縦線の間隔は重要ですね。縦線の無いところは、あとで波形がどうなっているかわからなくなります。もちろん細かく切れば切るほど波形の細かいところが表現できます。音も良くなります。ですから、できる限り細かく切っておきたいところです。
もちろん細かくしすぎると、今度はデータの量が増えてしまいますから、むやみに増やせるわけではありませんが、CDでは、人間が聴こえる周波数を十分に記録できるようにということで、一秒間に44100回の縦線が来るような、かなり細かいメッシュを使っています。
なお、こういうこういう風に、一定時間ごとに波形を切り刻むことを「標本化」と言います。英語ではサンプリングですね。一秒間に何回切るかを、サンプリング周波数なんて言い方をします。
CDは一秒間に44100回ですから、サンプリング周波数は、44100ヘルツ。または44.1キロヘルツというわけです。
次は縦方向の間隔です。
これも細かい方がいいんですが、ここでは練習のために、とりあえず10段階にしてみました。

では波形を数字に直してみましょう。ここで注意する事は、時間と同様、縦方向もステップの間は扱えない事です。つまり数字と数字の間はありません。小数はないわけです。
たとえば先頭の、時間「1」ところは、赤い波形は3.3くらいのところを通過しています。でも数字は3か4しかとれないので、3とします。次はどうしましょう。4ですね。
こういうふうに、中間の値を四捨五入して、一定の間隔の網目に乗せることを「量子化」と言います。
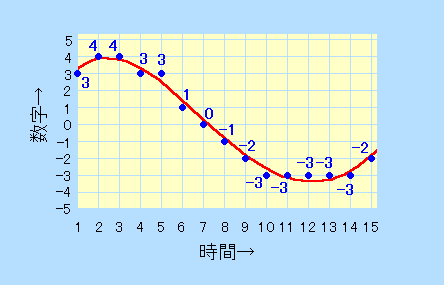
さあ、これで波形が数字列に変わりました。つまり波形のA/D変換ができたのです。では数字だけ取り出してみましょう。
![]()
この数字列が、波形がデジタル化された結果というわけです。この数字を記録するのがデジタル録音、伝送するのがデジタル伝送ですね。赤い波形はもう見えなくて、数字しかありません。
(制作/著作 かないまる 2000年7月15日)
(字句修正 2000年8月20日)