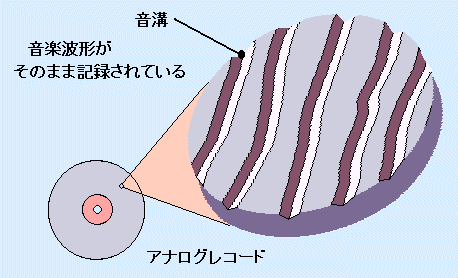
5.
波形のアナログ記録
このように、音の録音というのは音の波形を記録しておくことです。再生は、その波形どおりの電気信号を作り、スピーカを鳴らすわけです。
で、今パソコンを使って音を出しましたが、その音楽は、パソコンのなかのファイルに入っています。
で、このファイルの中身はあとで見ますが、同じ音楽を再生するのに、ちょっと前までは、テープレコーダやビニールのレコードを使いました。
これがどういうふうになっていたかを見てみましょう。
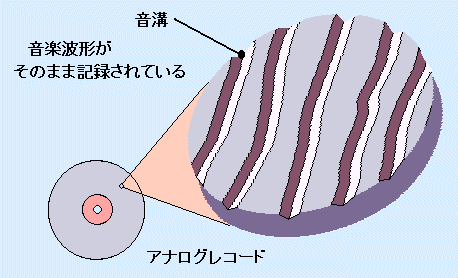
まずレコードです。これはもう抜群に分かりやすいですね。
こんなふうに、音楽の波形そのものが機械的に刻まれていました。再生するときは、この溝に針を下ろして、針の振動をマイクと同じ原理で電気信号に変えていたんです。
大昔は電気も使わずに、針の先に直接振動板をつけて音に変えていた事もあります。これはまさにエジソンが発明した原理のままですね。
レコードはエジソン以来約100年使われたわけです。
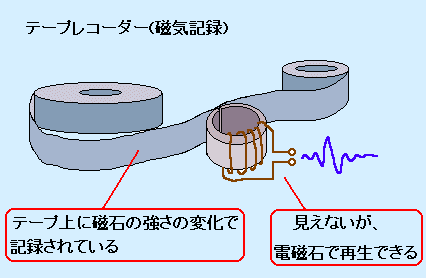
こちらはテープレコーダです。
テープレコーダのテープというのは、プラスチックのテープに磁石の粉を塗ったものです。だからこのテープは、実は磁石の帯なんですね。
で、磁石には強い、弱いがあるじゃないですか。強い磁石を近づければ、テープは強く磁化されます。弱く磁化すれば弱い磁石になる。そういう原理で波形を記録していたんですね。
この波形は目で見ることはできませんが、電磁石をテープに触らせてテープを動かすと、コイルから信号が出てくる仕掛けになっています。
記録するときも電磁石ですから、実は録音と再生は同じような感じになります(実際のテープレコーダでは、よほどの高級機をのぞいて、記録と再生に同じ電磁石を使っていました)。
ちなみにこのテープを日本で最初に作ったのはソニーですが、テープは紙製で、磁石の粉はペンキのように刷毛で塗ったそうです。
そんなんで音が出るんですからアナログというのはすばらしいものですね。で、このような記録は音の波形を物理的な量の変化に置き換えています。
レコードは機械的な形でした。テープは磁力ですね。
こういう連続した物理量で比例的に記録する方法を、アナログ記録といいます。
(制作/著作 かないまる 2000年7月8日)
(字句修正 2000年7月15日)