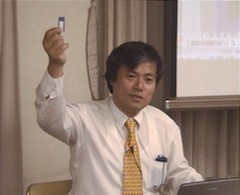
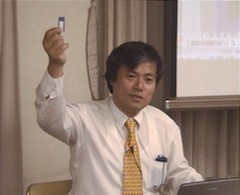
(ただいま講義中)
4.
変化するアナログ量--音の波形
前のページでは、体温計を、身の回りで最も簡単なデジタル機器の例として説明しました。そして、アナログ量を数字になおす、つまりデジタルにすることで、アナログのままではできないことが可能になる簡単な例を説明しました。
さて、体温計は一回測定値を表示すると仕事は終わりです。もし熱があれば、次に使うのはクスリを飲んで一時間後ですかね。熱がなければ、次は何カ月か後でしょう。体温という測定対象は変化を追うものではないわけです。
そこで、次に、もっと動きのある映像や音の場合を考えてみましょう。映像も音も基本は同じですので、ここからしばらくは、音の話で進めて行こうと思います。音のデジタル化。これを勉強します。
さて、皆さんは音が空気の振動であることはご存じでしょうか。音というのは人間の声や楽器が空気を震わせて、その振動を耳が感ずるわけですね。
ですから音の記録再生とういのは、この空気の振動の形を電気的に記録して再生することになります。
細かい話に入る前に、音と波形の関係をつかんでみましょう。まずこの下の図をクリックしてみてください。
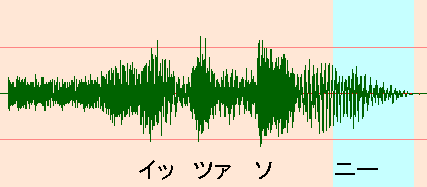
えー、ソニー製品、ご愛用ありがとうございます(^_^)。
使っているパソコン環境によりますが、うまく行けばソニーのコマーシャルの最後に流れる「It's a sony」が再生できたと思います(だめなかたはあきらめてください)。
音を聴きながら図を見ていると、波形の大きさと音の強弱が合っている様子がわかりますね。そう、この図は、このコマーシャルの音の波形の図なんです。
ただ、この図はあまり細かくありません。波形がどうなっているか分かりにくいですね。そこでブルーに色付けした「ニー」の部分を拡大してみましょう。
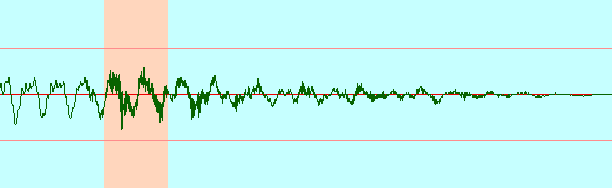
この波形図も、クリックすると音が出ますので、環境のある方は試してみてください。
こうして拡大してくると、だいぶ波形が見えてきます。先程の図では、音量の大雑把な変化がわかりました。それが拡大すると、かなり音の波形が見えてきます。
音の波形は、低い音はゆっくりした波形になります。大きな波ですね。高い音は速い動きをしています。上の図でもピンクに着色したところは、そういう成分があります。高い音の成分があるんですね。
そこでこの部分を、もう一度拡大してみましょう。
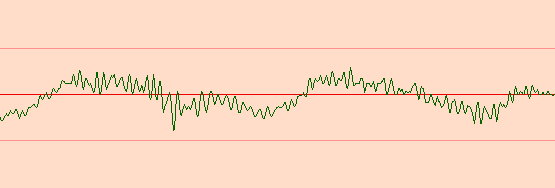
さあ、見えてきましたた。
この図も一応クリックすると音が出るようにしてあります。短すぎて分かりにくいかもしれませんが、あまり滑らかでないノイズ的な成分が聴こえると思います。
このページの冒頭にお話したように、音は空気の振動です。その振動の形を電気的にとらえて図にしたのが、この波形です。つまり録音、再生をするということは、何らかの手段で、この波形を記録しているわけです。
それと、
このページでは、そんな音と波形の関係を覚えておいてください。
(制作/著作 かないまる 2000年7月8日)
(字句修正 2000年7月15日)