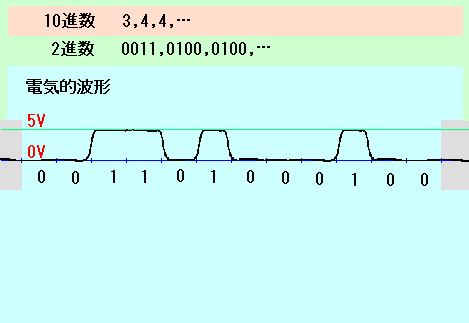
16.
デジタルは信号が劣化しにくい
さて、いままで見てきたデジタルの電気的波形は、実は理想的な状態の波形であって、実際にデジタル機器が内部で扱っている信号は、実はこんなにきれいではありません。
ちょっと本当の波形を見てみましょう。
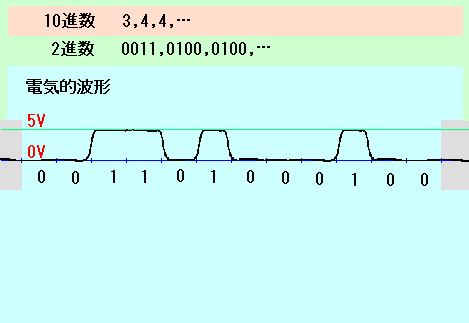
このように、まず角がだれています。また、よく見ると汚いですね。これはノイズが乗っているんです。
しかし、デジタルでは、この波形の形そのものを利用する訳ではありません。波形の形そのものを利用するのはアナログです。デジタルでは、すでにご説明したように、情報としては0か1かしかし見ていません。
上の波形は、0か1かという意味では、全然壊れていませんね。
実はもっと信号が汚くなっても大丈夫です。機器内部ではだいたい上の波形品質は出ていますが、この信号を電線で伝送したり、メディアに記録し、再生すると、波形は結構崩れてしまいます。
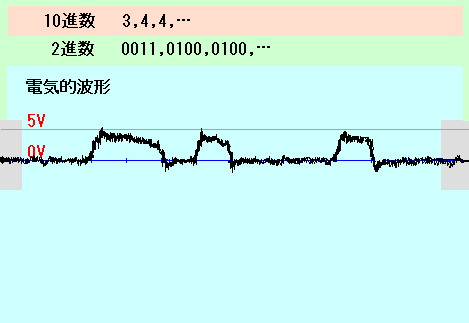
これは、デジタル波形を伝送し結果です。かなり汚いですね。信号に対してノイズが20%くらい入っていますね。S/N比でいうと13デシベル程度です。
これがアナログのテープやレコードみたいに、波形そのものがオーディオ波形だったら、もうシャーシャーとノイズだらけで聴けたものではありません。アナログレコードがだいたい50〜60デシベル。カセットテープレコーダーが40〜50dBですから、13デシベルはまるでひどい値です。
またレベルも下がっています。送り側は0-5ボルトで送ったはずですが、受け側では0-4ボルト程度しかありません。
それに、波形的にも立ち上がりが少しとんがっていたり、だれているところが有ったりして、全体に崩れています。
ところが、この程度なら全然問題はありません。勿論再生後音量が下がるなんてこともありません。
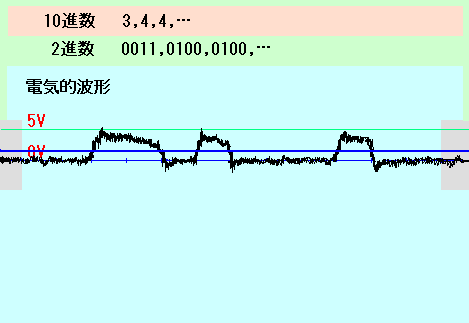
まずデジタルですから、この波形から、各ビットが0か1かを判定すればいいわけです。もちろん、電圧の高いところが1、低いところが0ですが、その判定基準がどこかにあります。
この判定基準は、おおむね高いところと0の中間にすればよく、上の図では青線となります。
(この青線は、データがオールゼロになると作れませんが、デジタル伝送では同期信号を入れたり、波形の送り方を工夫したりして、必ず1のデータの電圧を受信側でとらえることができるようになっています)。
つまり、この青線より高ければ1、低ければ0と判定すればいいのです。
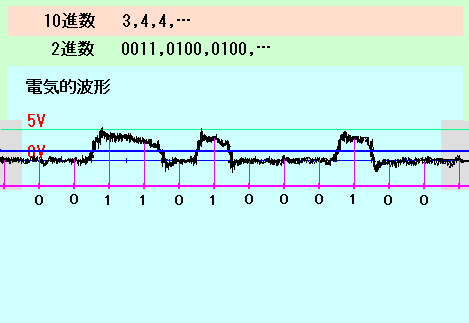
読み出すタイミングは、すでに学習したように、別のラインで与えられるビットクロックで読みます。このピンクの目盛りがビットクロックで与えた、信号の1・0を判定するタイミングです。
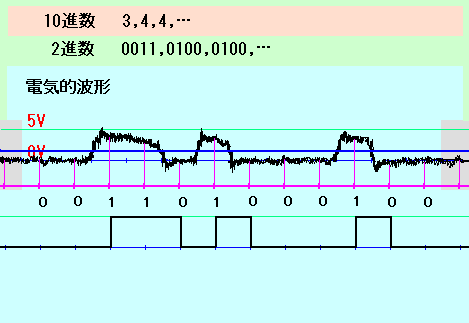
どうですか。このタイミングで0か1かを判定すれば、読むのに何の支障もないですね。
波形はあばれているようでも、ビットを読むタイミングでは、波形は結構安定していることがわかります。そして見事に1と0を間違いなく読むことができました。
(制作/著作 かないまる 2000年8月27日)
次のページへ