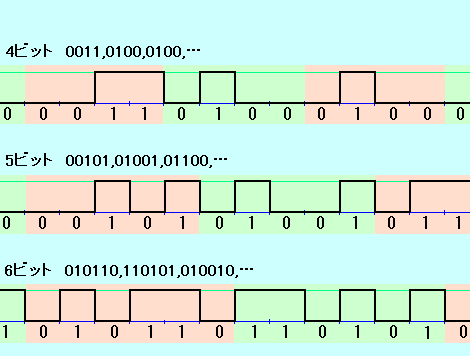
第五回です。今回はまずビットレートという概念を眺めましょう。
そのあと、デジタル化の最大のメリットともいえる、信号劣化が起こらない理由を学びます。ここまでの山場ですので、しっかりつかんでください。この概念に初めて触れる方は感動するかもしれませんよ。
(講座第五回分/2000年8月27日公開)
14.
ビットレートの話
さて、先程から例に使っているデータは、一つのデータが4ビットの語長(ワード長)を持っています。そして0011,0100,0100,…というデータ列を波形に直した例を見てきました。
これを5ビットにしたらどうなるでしょう。6ビットでは…?。
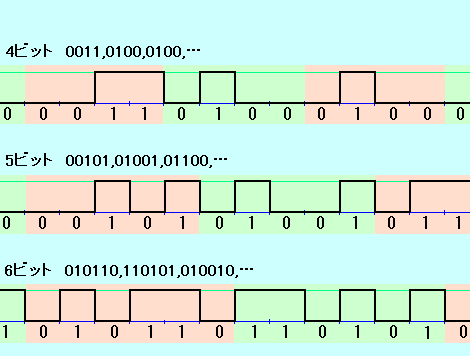
さあ、波形にしました。どうでしょう。4ビットでは図の中に3ワードが収まっています。ところが5ビットでは3ワード目が飛び出してしまいます。6ビットでは2ワードしか扱えませんね。
このように、一つのデータのワード長(ビット数)を増やすと、当然、伝送すべき総ビット数が増えてしまいます。また、一秒間に送るデータの数が増えれば、これもまた総ビット数が増えます。
上の図の横軸は時間ですが、上の例ではデータが増えているにもかかわらず、1ビットあたりの時間幅を同じで伝送しています。したがってビット数が増えれば時間がかかります。
一般に、ビット数を増やすのは、音質や画質を向上するためです。でも、一秒間に扱えるデータの数が多いこともクォリティーの一つですね。ですから、このようにビット数を増やしても送れるデータが増えない場合は質の向上には役に立ちません。
そこで一般的には、ビット数やチャンネル数が増えた場合は、インターフェイスを高速化し、またメディアを高密度化して、ビットをどんどん詰めて行きます。
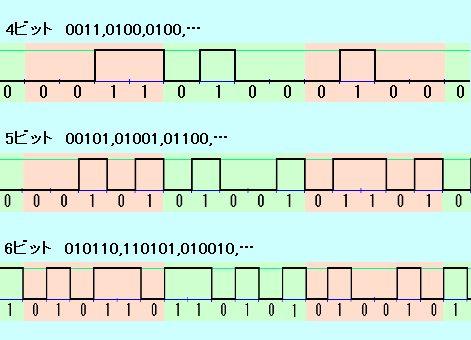
この図は、5ビットと6ビットの伝送でも一つのワードにかかる時間が同じになるように、ビットを詰めた例です。これをさらに16ビットにすると、4ビットの1/4の幅しかなくなります。
さらに、ステレオ2チャンネルを送るには、普通、L,R,L,R,と交互に送りますが、その場合はビット幅はさらに1/2にしなければなりません。つまり、上の図の4ビット(1チャンネル)の場合の1/8のビット幅になるわけです。もう上の縮尺では、図は書けませんね。
このようにビット数を増やすとそれだけ伝送は大変になります。また一秒間に表れるデータの数(これをサンプリング周波数といいましたね)も、大きくなるほど記録伝送は大変、ということになります。
(制作/著作 かないまる 2000年8月27日)
次のページへ