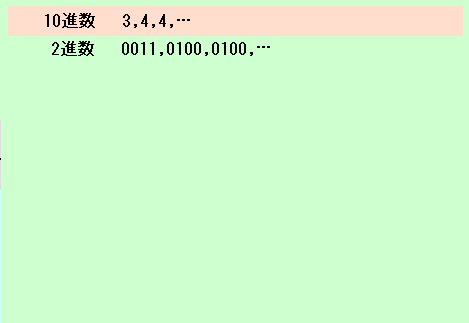
13.
電気の世界のデジタル信号
前回の講座で出てきたアナログの赤い波形。これを電話で伝えることはできませんね。「最初に上に行って、つぎに下にいく波の形ので…」。これは無理というものです。
でもこれを数字になおしたものは、たとえば電話で「さん、よん、よん、さん、いち…」と伝えることが可能です。数値化することで伝送や記録がしやすくなっているわけです。
しかし、機械同志が通信するには「さん、よん、よん、さん、いち…」とやるのは逆に大変です。機械が言葉を理解しなければならないからです(まあ、不可能ではないですが)。
しかし二進法にすると、機械同志が通信することや、記録しておくことが可能になります。つまり、0と1を低い電圧と高い電圧(または電流の有り無し)に置き換えてしまうのです。0と1しかなければ一本の電線で送ることができます。
この講座では電圧で話を進めましょう。前ページの二進法の数字を電圧の波形に直してみます。
もう一度先程の数字列を、先頭の3個だけ書きだしてみましょう。
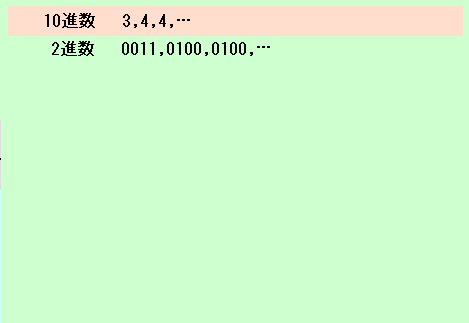
これに対応する電気信号は次のようになります。
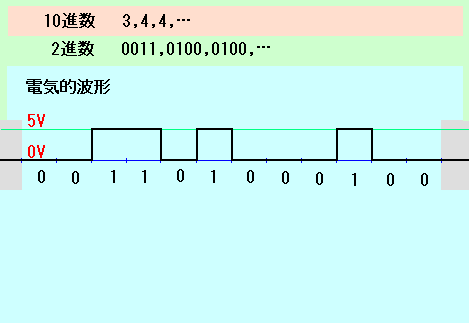
これが電気波形です。電気では普通、0を0ボルトにします。1はいろいろですが、CDプレーヤなどでは普通は5ボルトです。波形をじっと見て、頭から読んでみてください。たしかに0011,0100,0100になっていますね。
ただまあ、人間はこの波形を難なく0011…と読めてしまいますが、機械はまだそうは行きません。
連続している波形の、いったいどこで0/1を読んだらいいのか。それから、4ビットごとの切れ目も、この波形だけではわかりません。
そこで普通は、0/1を読むべき位置を示す信号(ビットクロック)と、ワードの固まりを示す信号(ワードクロック)を、データと合わせて使います。
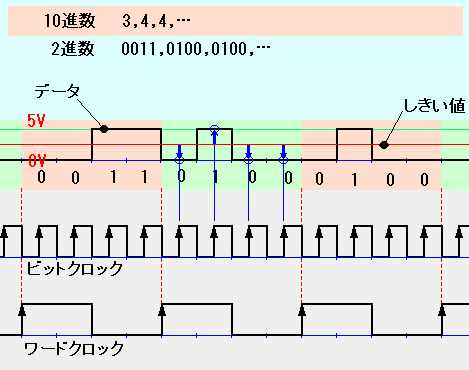
上の図は、ビットクロックとワードクロックを書き込んだ図です。
まずデータはビットクロックの0から1へのエッジで読みます。データは0ボルトと5ボルトの二つの値をとりますが、その中央の2.5ボルトを境目にして、それより低ければ0、高ければ1と読みます。(この境目を「しきい値(スレショールド)」といいます)。
ワードクロックもエッジで与えます。エッジからエッジまでが、1ワード=4ビット分になっていますね。
この講座では、このあとはクロックは書きませんが、機器の中では常に活躍しています。つまりデータとクロックは常にセットになっているのです。もちろんCDプレーヤなどの機器内には、こういうセットの配線を実際に普通に存在します。
しかし、CDの外にデジタル信号を出すときは、信号線は一本です。
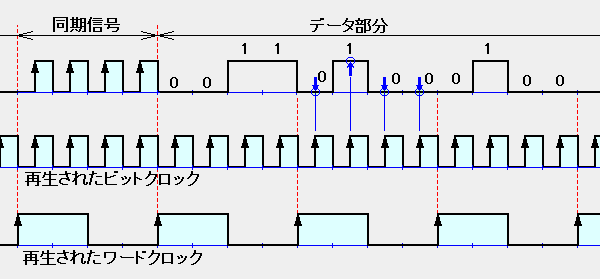
このような場合は、同期信号とデータを交互に送ります。そしてまず同期信号からクロックを作ってしまいます。これをクロックの再生といいます。
クロック再生は、インターフェイスがロックして最大で一秒くらいかかることがあります。短くても0.1秒くらいかな。ロックするまでは音楽は聴こえませんが、一度ロックすると再生されたクロックは連続したものになります。
もちろん音楽をかけていなくても電源が入っていればロックしますので、音楽の頭が切れるわけではありません。電源を入れたり、インターフェイスケーブルをつないでからCDを演奏するまでの間に十分ロックすることができるからです。
このような単線での伝送では、クロックの再生が重要な技術で、PLL(位相同期)という技術を使って行います。もちろん放送のデジタル化などでも使われる技術で、デジタル通信の非常に重要な技術の一つです。
(ちょっと難しい補足)
なお上記の同期信号とデータの形は、実際はもっと複雑なものが使われます。無線通信の場合は、この波形全体をさらに無線電波に乗りやすい形に変換します(変調といいます)。しかし、単線伝送、または無線伝送の場合は、同期信号で再生クロックを作り、そのクロックでデータを読むという基本は、どのような場合でも同じです。
それから、同期信号が来た瞬間はDA変換した波形が途切れるのかな、と思う方もいらっしゃるでしょう。でも、その心配はありません。実際は受信したデータは一度メモリに入れて、そこから一定の速度で読み出して使うからです。書き込みと読み出しのタイミングは違いますが、平均速度は同じで連続したデータにするわけです。
これをもっと進化させた場合、データ伝送速度はDA変換よりかなり高速にして、一定量のデータがメモリにたまると回線上にデータが無くなる(お休みする)ケースもあります。回線が空いている時間は別のデータを送ることもできます。これを時分割伝送といいます。
CDのデジタル伝送も、実はステレオ2チャンネルをL1/R1/L2/R2/L3/R3/…と交互に送っています。でもDAコンバータは2チャンネルあり、左右のDAコンバータは、それぞれが自分用のデータを使っています。これはL1/R1/L2/R2…と伝送されたデータを一度メモリにためて、たとえば右用のDAコンバータはR1/R2/R3/…という右用だけのデータを受け取って動作するからです。
(制作/著作 かないまる 2000年8月20日)
(2000年8月27日 末尾の記述を削除し15ページに移動)
(補足を追記 2001年6月2日)