| Q&A |  |
| Q&A |  |
このページはQ&Aです。とりあえず自宅に見えた方の素朴な質問を、Q&A形式にまとめてみました。メールその他でご質問いただいた場合、このページは増殖します。ご質問大歓迎です。
| [Q1]サブウーファは必要ですか。 |
基本的には上手に使えば有ったほうがよいケースが多いのですが、無くても何とかなることも多いと思います。って、あまり役に立たない返事だな(^_^;)。
言いたいのは、5.1チャンネルだから0.1チャンネル用に使うんだと思いこんでいると(思い込んでいるでしょ)、そうでないこともあるということです。
-------------
そこでまず、5.1チャンネルが生れたワケを書きましょう。
5.1チャンネルは、5個のメインチャンネル(フロントL/R、サラウンド(リア)L/R、センター、LFE(低域専用))で構成されています。そしてこのLFEチャンネルは、映画館の都合で生れたものです。
このLFEは、メインの5チャンネルのスピーカの低音が出ないから使うわけではありません。低域の再生帯域は実は十分あります。その証拠に、映画では音楽ではあまり使われないような低域成分を観客の心理状態をコントロールするために結構多用していますが、意外なことにLFEではなくメインチャンネルが使われることが多いのです。多分それは、音の基本的クォリティーがメインチャンネルのほうが高いからだと思います。
しかしメインチャンネルの低域はあまり大きな音は出せません。ドカーンという爆発シーンや宇宙の戦闘シーン(なぜ音がするんだろう(^_^;))等では、音量が足らないのです。
そこでここぞというとき用に音量稼ぎ専用に作られたのが、150Hz以上の帯域がない低音専用の LFE(low frequency effect)チャンネルです。
ここで話を整理してみると、
ということになります。
これに対して、家庭でのサブウーファは、LFE専用ではありません。メインチャンネルの帯域が足らない場合、これを補う役割もあるのです。。
SDP-EP9などに入っているバスマネージメントは、低域の出せないチャンネルの低域を吸い取って、低域の出るチャンネルに回したり、サブウーファがある時は、その足りない帯域と、LFEをサブウーファに回すことが出来ます。この機能は非常によくできていて、ほとんどの場合これでうまく行きます。
しかしより高度な再生音を目指した場合、機械に任せずに、自分でメインチャンネルのスピーカにサブウーファを直接つないで、細かい調整をしたりしたほうがずっと高級な音が出ることも有るのです。
| [Q2]その具体的な例を教えてください |
例えばブックシェルフ型のスピーカで50Hz〜70Hz程度までしか帯域が無い場合、サブウーファを使って1オクターブほど再生帯域を下げると、非常に大きな効果が感じられます。
この場合基本はSDP-EP9で各メインチャンネルをsmallに設定して、カットオフ周波数を調整し、LFEともどもサブウーファから出す手法です。
しかし包囲方向感を重視する場合はフロントとサラウンドを別のサブウーファ(つまり二本)にすると結構いい感じになります。サブウーファの音源ははメインのスピーカ信号からもらいます。LFEはSDP-EP9をサブウーファをNOに設定すればメインチャンネルに出てきますから、その低域もろともサブウーファで増強します。100Hz前後の帯域はメインチャンネルのスピーカも活躍しますから、この方法は最大音圧も高く取れます。
これと似ていますが、フロントは直結で帯域を拡大し、サラウンド(リア)をsmall、サブウーファをYESにして、LFEとサラウンドの低域をサブウーファから出す手法も有効です。
そのほか過去やってうまくいったのは、下記のような設定です。
| [Q3]かないまる邸のサブウーファの使い方を教えてください。 |
Q1で述べたように、かないまる邸はフロント大型(センターはファントム)、サラウンド小型のケースです。
本文で述べましたが、かないまる邸では現在サブウーファを使っていますが、これまでの過程でいろいろな使い方をしてみました。それぞれに楽しめるので、経過とともに解説しましょう。
-------------
前提として使用しているスピーカをもう一度確認しておきます。
まずサラウンドスピーカは米NHT製のsuper Zeroです。小型で密閉型なので低域は全然出ませんが、サブウーファとつなぐのは比較的楽ですし、トーンで持ち上げれば一応レスポンスはあります。
一方、フロントスピーカは英ハーベス社製 monitor HL type4。20センチウーファを比較的大型の箱に入れて、軽いダクトで低域を拡大したもので、ウーファー径からは信じられないほど豊かな低域が出ます(同じ箱なら30センチスピーカより20センチスピーカのほうが周波数レンジ的には楽に低域がのびるのです)。
| 方法1.サブウーファ無しで標準的設定 |
サブウーファ無しの場合標準的な設定です。
この設定は、SDP-EP9が smallに設定されたNHTの低域を抜き取り、largeのハーベスに注入します。LFEもハーベスから出てきます。
この設定では、サブウーファ無しでも比較的豊かな低域の量感が得られます。
一番手軽でいいんですが、やはり低域が全部前方に行ってしまうため、5本全部largeのスピーカを使った音場と比べると、包囲感が薄れる難点があります。
もちろん中域以上の方向感は問題なく、もともとサラウンドの低域成分の無いドルビープロロジックよりは、はるかに豊かな臨場感があります。
| 方法2.サブウーファ無しで、リアをlargeに設定 |
スピーカの設定を全部largeにして、サラウンドの低域不足はSDP-EP9のイコライザ機能を活用する方法です。
同時にSDP-EP9のイコライザーをonにして、カットオフを99ヘルツ、レベルを+6〜+9dBに増強します。
この状態は、各チャンネルの低域はそのまま元のスピーカから出てきます。またLFEは1/4の音圧にして各スピーカに注入されます。
結果は上々で、低域の方向感が復活し、包み込むような感じが出てきます。
しかしさすがに+6〜+9dBでは、アンプもスピーカも厳しくて、音量を上げると破綻してしまいます。
この設定は結構長い間使っていまして、リビングのような小さな空間でも低域の方向感が重要なことが確認出来ましたので、いよいよサブウーファを導入することにしました。
| 方法3.サブウーファありで、教科書的設定 |
導入したサブウーファは、比較的小型で床スペースを取らないソニー製のSA-W301で、ラックの脇に置きました。
まずは教科書的に、プロセッサSDP-EP9にサブウーファをつなぐやり方です。
この接続は標準的なもので、まずsmallに設定されたサラウンドスピーカの低音がサブウーファに出てきます(SDP-EP9は低域抜き出しのカットオフ周波数が可変出来ますが、100Hz程度が良いようでした)。
またLFE信号もサブウーファのみから出てきます。フロントには行きません。
この設定は、標準だけあってなかなかよくできています。方向感や包囲感も申し分ありません。
ただ、サブウーファが小型のせいか、LFEをハーベス経由で出したときに比べるとやや迫力が欠けます。
また音量を上げると、絶対音圧もやや足らない感じがしました。TA-F5000は35Wしかないアンプですが、メインのスピーカはまだ全然余裕が有るのに、サブウーファが先に限界に来てしまうのです。
まあ、自宅とはいえデモをやることがあり、そのときの音量が結構高いということもあるんですが(^_^;)。
| 方法4.サブウーファをNHTと直結 |
そこで最後の案として、SDP-EP9はサブウーファをNOに設定してLFEを各スピーカに分配した上で、サブウーファはNHTのスピーカ信号を与える方法を試しました。
この設定では、LFEの配分については方法2.と同じになります。つまりLFEは1/4にした上で、4本のチャンネルに等配されます。
この方法は、元の低域の方向感や包囲感がほとんど崩れません。またLFE再生にフロントスピーカも活躍しますので、十分迫力が出ます。
サブウーファはラックの脇ですから、聴取位置の真横からやや前程度の位置で、神経質に考えればサラウンドスピーカから離れていて気になります。
でも、フロントから十分に離れていれば立体感はちゃんと残りますし、経験的にはサブウーファが横にあるというのは、結構いい感じになることが多いようです。
| [Q4]暗いところで大画面を見ていてつかれませんか |
被写体から適当な距離をおき、画面の両端は背景として扱われています。この背景を全部見ようとして意識すると疲れます。しかしこの背景は、それが広いことで、観衆を映画の世界に引き込むためのものなので、無理に見なくてもよいのです。
この大画面になれてしまうと、むしろ明るいところで小さな画面で(つまりテレビで)映画を見る方がよほどつかれます。被写体が小さくなり過ぎますし、暗い場面はよく見えません。暗いところで見るべきものをあかるいところで見るから、これは当然です。
しかし以上は映画の話で、テレビ放送を大画面で見ると、基本的には疲れます。なぜならテレビは小さな画面を明るいところで見るように作っているからです。
一例を上げるとアップの頻度。テレビを見ていると基本的にはアップの連続です。これを大画面で見ると、もうどうしようもなく疲れます。テレビも年々大型化しているのですから、もう少し作り方を変えたらどうかと思うんですが。
ただ、サッカー中継のようなスポーツ中継は、アップにしてしまうと全体が判らないので、結構引いたシーンが多く、大画面に向きます。もう少し引いてくれるともっといいんですが、それだとテレビで見るとなんだかわからないかもしんない。
| [Q5]壁の色は白はいけないと聞きましたが |
しかしリビングの壁を黒くするのは、いくらなんでも反対です。リビングはやはり明るい空間であって欲しい。だからかないまる邸のリビングAVはわかっていてやっていることなのです。
とはいうものの、かないまる邸のスクリーンは、割合条件は良い方です。
というのは、プロジェクタを天吊りにした場合、一次反射は床方向が最もきつくなりますが、床方向は暗めの色調のテーブルにしてあるからです。ここが白いテーブルだと、完全にアウトです。
あとは左側は壁が遠く、右側もすぐ近くは木部の柱で、そのあと出窓に切れて行きます。だから二次反射が見ている人に届きやすい、割合距離のあるところからの反射は意外に少ないのです。
あとはD50で80インチという贅沢な使い方ですね。元々の映像に力がありますから、多少の劣化は気にならないようです。
| [Q6]AC-3は5本全部同じスピーカを使うのがよいと聞きましたが本当ですか |
映画館のスピーカは、フロントはスクリーン透過型ですから極めて条件が悪いのです。これに対してサラウンドは直接放射ですからかなり楽です。つまりそもそもかなり音色が違う。
しかし映画の世界には専門のエンジニアがいて、このへんの音色を問題の無いレベルまで合わせ込んで行きますから、フロントとサラウンドのつながりはとてもよくできています(日本の映画館ではあまりいいなと思ったことはありませんが、カリフォルニアの映画館の音を聴くと、とても見事です。ダビングシアターももちろんよくできています)。
しかしホームAVユーザが、音色の違うスピーカをうまくつなぐことが出来るかというとなかなか難しいのですね。最初に毛色の違い過ぎるものを選んでしまうと、どう頑張ってもつながりません。
かないまる邸で使っているハーベスは、もとがBBCmonitorのエンジニアが作ったものですから、わりと素直なモニター調です。NHTはアメリカ製ですが、これもわりと素直系で、そもそも素性は似ていて、そのせいか結構うまくつながりました。
これを例えば、サラウンドにボーズやJBLを持ってきたら、果してつながるか。私はつなぐ自信はありません。
| [Q6]ビーズスクリーンとマットスクリーンとは、どう違うのですか (98/07/06 追記)。 |
| 原理 |
また反射の方向も、ランダムです。つまりプロジェクターから当たった光は、いろいろな方向に満遍なく反射します。ですから例えばスクリーンの横から見ても、画面がはっきり見えるのがマットの特長です。
これに対してビーズタイプというのは、塗料に微細なガラス玉を混ぜてあります。直径の数字は忘れましたが、ガラス玉といっても微細なものです。
このビーズは塗料の表面から顔を出していて、そこに入った光は内部で全反射して戻ってきます。そして『光が入った方向』の反射光の強度を上げてくれます。
この方向性は、それほど強いものではありませんが、それでも周辺への反射は抑えられますので、スクリーンを横から見ると暗くて、投射方向から見ると明るいという特性になります。
そしてマットタイプに比べるとこの正面の明るさは2倍以上ありますが、これをゲインと言い、2.5〜3程度が普通です。
| 両者の特質と画の見え方の違い |
一般論ですが、マットタイプのほうが自然でしっとりしていると言われます。画面内の均一性もマットのぼうが高いです。これに対して、ビーズタイプは中央がやや明るくなることが多いのと、幾分画質がキラキラする傾向になることがあります。
ところがこれはあくまで一般論で、ビーズタイプのものも非常にしっとりしたものがあります。ソニー製のビーズは良い部類だと思いますが、オーディオフェアでセッティングしてもらい、期間中ビーズタイプであることに気づかなかったこともありました。まあ、フェアと家庭は条件が違いますが、それにしても最近のビーズは良くできています。
ちなみに私が使っているのはキクチ科学のマリブというマットタイプですが、これはスクリーン自体はスチュワート製です。スチュワートは北米のサンウドスクリーンの大半を抑えているメーカだそうで、その色の自然さはさすがです。
| [Q7]777ESや828Xでバイワイアリング接続はできますか。
(2000/07/18 追記)。 |
| バイワイア接続の原理 |
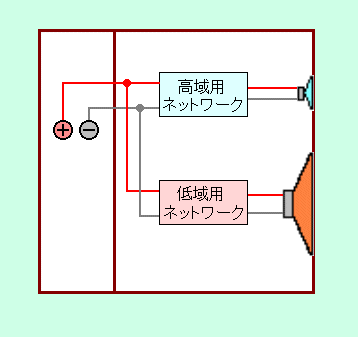
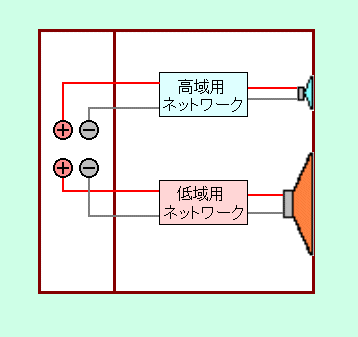
| バイワイアリング接続の実際 |
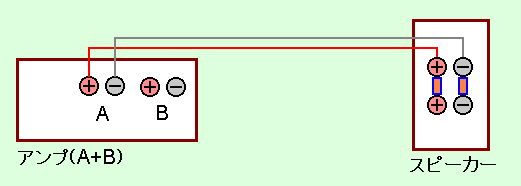
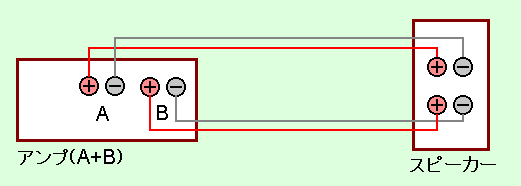
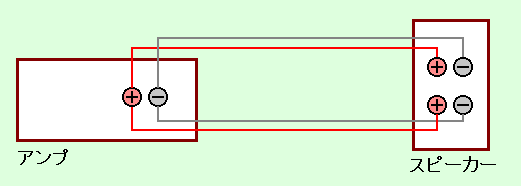
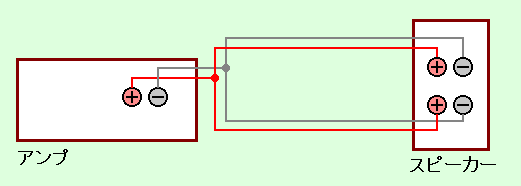
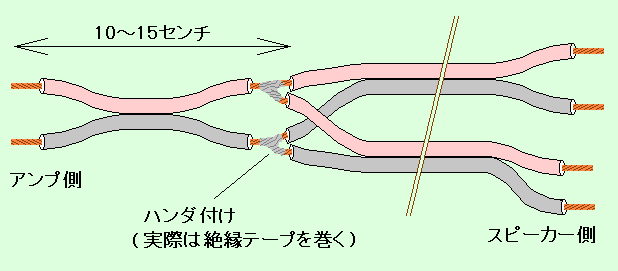
| バイワイアリングに関する、よくある質問 |
このページに対するご質問は、
GEE01151@nifty.ne.jp までお送りください。