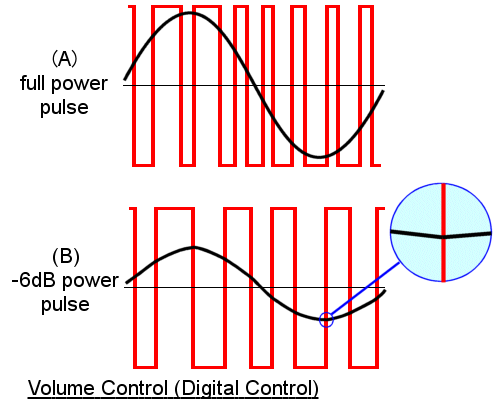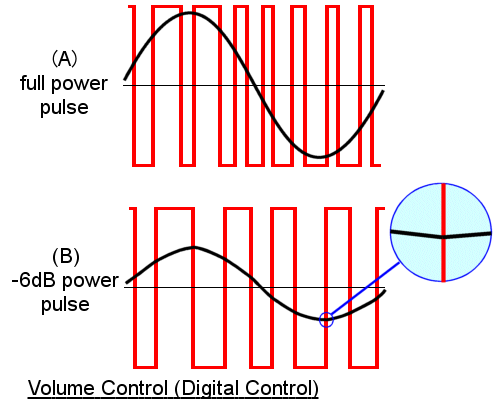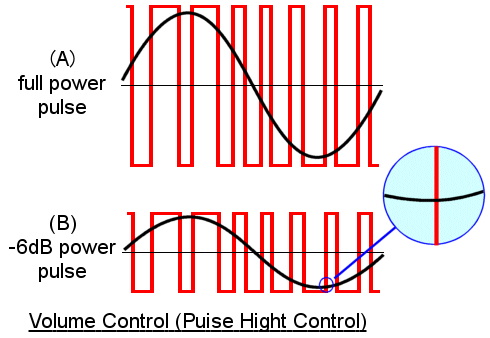S-Master PROとは (1)
パルスハイトボリウム
更新 040517
初稿 040502
前ページまでで解説したS-Masterは、ソニーのデジタルアンプのコモンテクノロジーです。つまりDAVと呼ばれるDVD一体型のシステムステレオから単品まで、一気通貫で登載されている技術です。
しかしTA-DA9000ESは、世界一の単品コンポーネントを作るため、この世界一のS-Master技術をベースに、さらに数々の工夫や新開発を行いました。こうして生まれたのが、単品コンポーネント用のS-Masterである、S-Master PROです。
したがってS-Master PRO方式はS-Masterの特長をすべて含みます。そして追加されて技術とは、パルスハイトボリウムとDCフェイズリニアライザーの二つです。
2. パルスハイトボリウム
ではまず、バルスハイトボリウムから説明しましょう。
S-Master方式はフルデジタル方式であるため、基本的にはアナログ的な音量可変の仕組みを持っていません。したがって音量を変化させるときは、デジタルデータそのものを計算で小さくする必要があります。
この図はそのイメージ図ですが、パルスの高さは一定で、パルスの構成が変わります。ところがデジタルデータ上で音量を絞ると音質が劣化します。
たとえば45という十進法の数字を1/2にするとします。結果は25.5です。でも整数しか使ってはいけないとすると、25、または26と表現するしかありません。0.5は失われるのです。これと同じことが二進数でも起こります。
二進法では音量を半分にする、つまり6dBを絞る毎に、1ビットのデータを失います。16ビットのデータは音量を半分にすると15ビットになってしまいます。家庭では18dB程度絞っていることが多いですから、これだと3ビットもなくなってしまうわけです。
これが「ビット落ち」と言われるもので、音量をしぼると歪みノイズが増加したり、情報量が少なくなったりして音質が劣化します。
パルスハイトボリウムは、パルスの構成は音質のよいフルボリウムの状態のままで、アナログ的な手段でパルスの高さを変えることで音量をコントロールします。したがって音質は劣化しません。
3. 原型はカレント i ボリウム
パルスハイトボリウムの原型は、TA-E9000ESにあります。
TA-E9000ESのD/Aコンバータは、カレントパルスD/Aコンバータでした。カレントパルスD/Aコンバータは電流源をスイッチングする方式ですが、この電流量を変化させることで音量調整をしていました。これがTA-E9000ESの「カレント i ボリウム」ですが、これも一種の「パルスハイトボリウム」です。
TA-E9000ESのときはビット落ち回避が目的ではなく、むしろ通常のアナログ式ボリウムよりS/Nが高くなることを目的としたものでした。通常のアナログボリウムは-6dB付近でノイズが増え、それ以下もあまりノイズが下がりません。つまり実用領域のS/Nはカタログデータの数値が出ないのが普通であり、TA-E9000ESはこのへんの打破を狙ったのです。
TA-DA9000ESのパルスハイトボリウムも、実はビット落ちの防止以外に、カレント i ボリウム同様のS/Nの改善効果が存在します。つまり音量を絞ると同時にノイズも小さくなりますので、高S/Nを保ったまま音量を絞ることができるのです。
なおパルスハイトボリウムと同じ原理のボリウムコントロールはT社の商品でも行っています。しかし、もちろんTA-E9000ESの方式のほうが先行して開発、発売されており、別にT社のまねをしたわけではありませんです。
これでS-Master PROの一つ目の特長がわかりました。それは、ビット落ちしない (音質が良い) パルスハイトボリウムという仕組みを持っているということです。
目次をフレーム表示する(目次がないときクリックしてください)